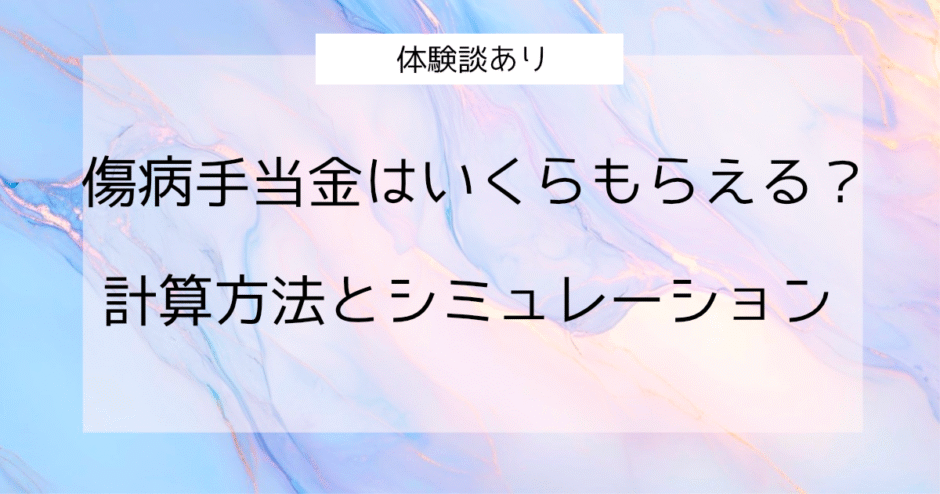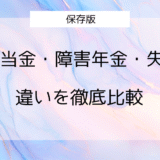「傷病手当金はいくらもらえるの?」「計算がむずかしい…」という不安、めっちゃわかります。
この記事では基本の計算式から具体例のシミュレーション、さらに私が実際にもらった支給額まで、休職中の資金計画に役立つ情報をまとめて解説します。
- 傷病手当金の計算式(標準報酬日額の出し方)
- 月収別の支給額シミュレーション表
- 私の実際の受給額とギャップの理由
- かんたんに支給額を確認する方法
※「振込はいつ?」が気になる人は先にこちらをどうぞ →
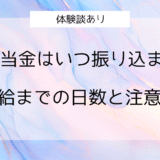 【体験談あり】傷病手当はいつ振り込まれる?支給までの日数と注意点
【体験談あり】傷病手当はいつ振り込まれる?支給までの日数と注意点
傷病手当金の基本の計算式
傷病手当金は次の式で計算します。
標準報酬日額 × 2/3 (約67%)× 支給対象日数
標準報酬日額の出し方
- 標準報酬月額を確認(健康保険の等級。給与明細や健保に確認でOK)
- 標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30
- ボーナス(賞与)は含まれません
- 支給には上限額があります(年度で更新。最新は所属健保の案内を確認)
「標準報酬月額」は過去の給与を基に決まる“保険上の月収の目安”です。額面給与と完全一致しないことがあります。
Q2:傷病手当金の支給額は、いくらになりますか?
A2:1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/?utm_source=chatgpt.com
月収別の支給額シミュレーション
ざっくり目安を知りたい人向けに、代表的な月収での試算を出してみます。
※計算は「30日休業」の例。実際は待期や出勤日などにより支給日数が変わります。
| 例の月収 | 標準報酬日額(概算) | 1日あたりの支給額(2/3) | 30日休業の支給額目安 |
|---|---|---|---|
| 月収20万円 | 200,000 ÷ 30 = 6,667円 | 6,667 × 2/3 = 4,444円 | 4,444 × 30 ≒ 133,320円 |
| 月収25万円 | 250,000 ÷ 30 = 8,333円 | 8,333 × 2/3 = 5,555円 | 5,555 × 30 ≒ 166,650円 |
| 月収30万円 | 300,000 ÷ 30 = 10,000円 | 10,000 × 2/3 = 6,667円 | 6,667 × 30 ≒ 200,010円 |
※上記は概算です。実際は「標準報酬月額の等級」「支給対象日数」「上限額」「調整」により変動します。
私の実際の支給額は22万円でした【体験談】
私の場合は毎月約22万円を受け取っていました。
これは残業続きで月収が多くなっていて「標準報酬月額」が約33万円に設定されていたため、その2/3が傷病手当金として支給されるからです。
- 標準報酬月額:約330,000円
- 標準報酬日額:330,000 ÷ 30 ≒ 11,000円
- 支給額:11,000円 × 2/3 (約67%)× 30日 ≒ 220,000円
ただし、ここから社会保険料(健康保険・厚生年金など)を自分で納める必要があります。
傷病手当金そのものは非課税なので所得税・住民税はかかりませんが、社会保険料は別途支払いが発生します。
私の場合、毎月会社に社会保険料(健康保険・厚生年金など)を約6万円支払う必要がありました。
そのため、実際に生活に使えるお金(可処分所得)は約17万円です。
「振込額=自由に使える額」ではないので、生活設計の際は社会保険料を差し引いて考えるのがおすすめです。
こうして実際の支給額を計算式に当てはめると「なるほど、そういう仕組みか」と腑に落ちました。
かんたんに支給額を確認する方法
- 給与明細や健保の通知で標準報酬月額(等級)を確認する
- 標準報酬日額 = 月額 ÷ 30 を計算する
- 標準報酬日額 × 2/3 × 支給日数で概算を出す
さらに確度を上げたい人は、所属する健康保険組合のシミュレーターやコールセンターに問い合わせるのが最速です。
(協会けんぽ等の公式リンクは各都道府県支部ページを参照)
関連:
よくある質問(FAQ)
Q. ボーナスは支給額の計算に入りますか?
A. 入りません。標準報酬月額は原則として月々の報酬ベースです。
Q. 扶養や税金で手取りはいくら?
A. 傷病手当金自体は非課税ですが、社会保険料など別コストの影響で、最終的な手取り感は人によって変わります。資金計画は少し余裕を見ておくのが安心です。
Q. 上限額はどこで確認できますか?
A. 所属の健康保険組合(協会けんぽ等)の最新案内で確認してください。年度更新があります。
Q. 傷病手当金はいつまで受け取れる?
A. 休職してから1年半です。
まとめ|目安を持って、余裕ある資金計画を
- 計算の基本は標準報酬日額 × 2/3 × 支給日数
- 「等級・対象日数・上限額」で結果がブレるので公式で最終確認を
- おおまかな目安がわかれば、休職中の家計が立てやすくなります